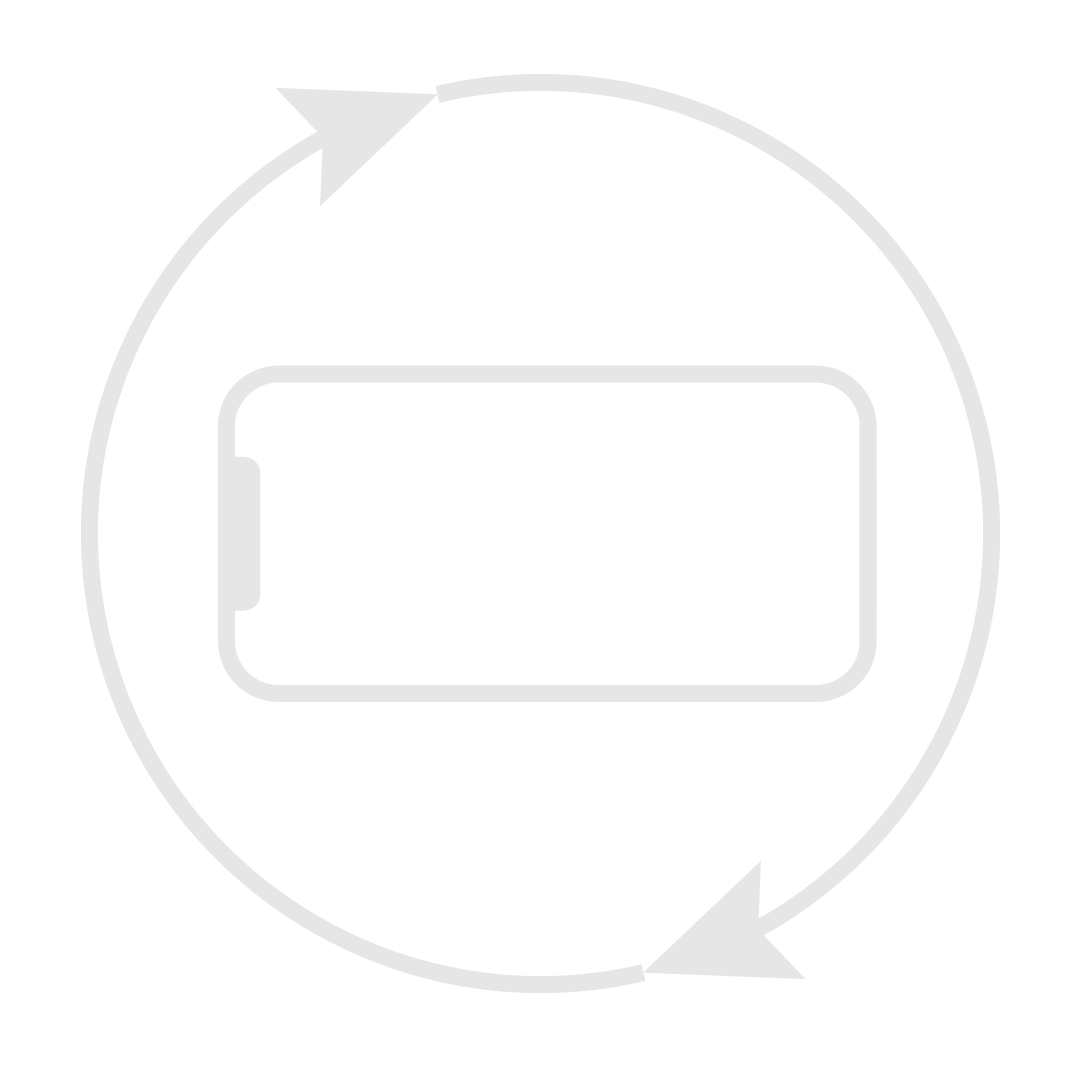白川町で、こども食堂や居場所支援事業を行う『Share living 日和 こども食堂』代表の尾関幸(おぜきさち)さん。
実家は白川地区の洞雲寺。現在はその末寺でもある白北地区の廣通寺*で暮らしています。
「『こども食堂』って名前だけど、親子だけじゃなくてみんなの食堂。だから年齢関係なく、気軽にいろんな人に来て欲しい」
こども食堂の開催の想いやこれまでのことをお伺いしてきました。
*廣通寺(こうつうじ):曹洞宗の寺院。町の指定有形文化財に指定された山門鐘楼があり、七堂伽藍が整備されています
「できるかも」はとりあえずやってみる
——2025年から始まったこども食堂ですが、毎回100名以上の方が来られているとお聞きしました。
始める前の想定では子ども30食、大人30食の予定だったけど、その2倍いきましたね(笑)
やっぱりやってみないと分かんない。やる前は、こども食堂を必要としてる人が白川町にいるのかも分からなかったし…あえて人数制限を設けなかったんです。
でも「できるかもしれない」って思うことは、とりあえずやってみる。それでここまできた感じです(笑)

白北ふれあいセンター(公民館)で定期的に開催されているこども食堂。写真は2025年8月に開催された第2回の様子
——やってみたら、2倍以上必要としている人たちがいたと…(笑)そもそも幸さんがこども食堂を始めるきっかけはなんだったんでしょう?
私は白川地区の和泉にある洞雲寺の長女として生まれたんです。小っちゃい頃から大きな法要の度に、お檀家さんとお寺で料理をつくって参拝されたみなさんに振る舞ったり、お彼岸には家族みんなでお団子をつくったり、年末には餅つきをしたりしていて。それが私が食に対して興味を持った原点なんだと思います。
主人も料理が好きなんです。一緒にキッチンに立つこともあって、夫婦で「いつか廣通寺でこども食堂とかカフェをやりたいね」っていう話はしていました。
——お話を聞いているだけでも賑やかさが伝わってきます…!自分が好きな”食”を通して、お寺をより地域に開かれた場にしていくというか。
でもコロナ禍が始まって人と会うことが少なくなって、そのタイミングで妊娠出産を経て、子育ての忙しさから育児以外考えられなくなりました。
そんな時に、児童委員をされてる方から「こども食堂に興味ない?」って声をかけられたんです。私は昔保育園で給食をつくっていて、その方はそのことも知ってみえるから「どうしてもやって欲しい」って。

幸さんに声をかけた方を含め、多くの方が『Share living 日和 こども食堂』の正会員、協力会員として幸さんをサポートします。「世代を超えてみんなが手伝ってくれて、そこでも繋がりが生まれてる」
——白川町ではそういう”やりたい人”のところにどんどん声が集まってきますよね(笑)
もちろん私も主人もやりたい気持ちはあったけど…「子育て真っ最中だしなぁ…」って感じでしたね(笑)主人と2人で相談して「ちょっと今は無理だね」ってことになって、ずっと断り続けていました(笑)
でもある時『ハチドリ基金*』っていう助成金のチラシを見せてもらって「これを受けながらやってみるのはどう?」って言われたんです。
それで「助成金があるなら、ちょっとやってみようかな」みたいな(笑)
*ぎふハチドリ基金:NPOなど市民活動団体の活動を資金面から支え、子ども・若者・子育て家庭を支える仕組み
こども食堂の前身は”ママ友会”
–——きっと幸さんは、いろんな要素から”できるかどうか”のイメージを膨らませているんですね。そこに助成金も加わって「できるかもしれない」と思ったというか。
あとは、仲の良いママ友家族で月1回バーベキューをしていて、その経験も大きかったですね。
4月から11月まではバーベキュー、12月から3月までは鍋をして(笑)それはお父さんの参加率もすごい良くて、去年のクリスマスは45人ぐらい集まったんです。

廣通寺で行われたクリスマス会の様子
——すごい、45人の鍋…(笑)
小さい子どもがいると、どこかに出かけるとしたらお父さんかお母さんのどっちかは絶対子どもを見てなきゃいけないんです。
でもこの会では、お父さんもお母さんもみんなで喋って、子どもは子どもたちだけで遊んでる。なんかそれがすごい良いなと思って。
——なるほど。
大きい子は小さい子の面倒を見てくれたりするから、同級生同士じゃなくて気が合う子たちで遊べる。なんか…お互いがお互いのことを思うというか。
私たちが子どもの頃って、こんなふうに近所の子たちと年齢関係なく遊んでたんです。でも今は子どもの数が減って近所にはぜんぜんいないし、子どもたちがいっしょに遊ぶことができない。

こども食堂の会場には『仲良し広場』というスペースが設けられていて、子どもたちの遊び場になっています
——みんなで集まってご飯を食べることで、親も子もそれぞれの時間を楽しめるというか。
そういうことも毎月してるから「できそう」と思ったのかもしれない。
助成金もそうだけど、ママ友とか公民館のなかで協力してくれる人が見つかったり、いろんな条件が揃ったの。タイミングが合ったというか。
——「できそう」から実際にやってみて、どうでしたか?
楽しい!めちゃくちゃ楽しい!子どもたちのイキイキした表情や弾む声を聞けると嬉しい!
それはボランティアスタッフも同じ気持ちで、参加者みなさんのたくさんの笑顔は原動力になっていますね。

こども食堂では、公民館講座とコラボして農業体験も実施しています。この日はさつまいも掘り!
突き進んだ自分の道
——幸さんのこれまでのこともお聞きしたいです。
昔からよく洞雲寺のお檀家さん方に遊んでもらったり、相手をしてもらいましたね。そんな環境の中で、お檀家さんから「お婿さんをもらってお寺を継ぐんだよ」みたいなことはちょくちょく言われてました(笑)
ただ私は小学生の時は保育士になりたい夢がありました。中学生の時は(白川町の)姉妹都市のピストイア市へのホームステイで食べたイタリア料理に感動して、元々食に興味があったのもあって、調理師になりたい気持ちが強くなりました。

幸さんがピストイア市へホームステイした時の様子
——やりたいことがあると「お寺の跡を継いで」というのは、息苦しくなりませんでしたか?
ちょっと向き合う時間が欲しかったんですよね、たぶん(笑)
高校はバレー部に入って下宿して、そのあとは「料理の勉強がしたい!」って言って京都の調理師学校に行かせてもらいました。一人暮らしをしながら落ち着いて考えたかったし、それに京料理とか精進料理も学びたくて。両親は反対しましたけどね(笑)
——生まれ育った環境を離れて、自分のやりたいことをやる。そこで自分の気持ちと折り合いはつけられました?
なんにせよ、帰ってくるのは決めていましたからね。
妹もいるんだけど、まあたぶん私かなっていうのは感じ取っていたというか。お寺に戻った後の未来がどうなるかは分からないけど、時間の許す限りは自分の道を突き進みたかったんだと思う。
はじめは反対しながらも、最終的には背中を押してくれた両親には感謝しています。
それで調理師学校を卒業した時、ちょうど保育園の調理師の求人があって!昔は保育士になりたいと思ってたから「保育園で給食つくるって、アリだな」って(笑)

夏休みに廣通寺で開催された、子どもたちの勉強会の様子。当時の経験が、今の活動に活かされています(幸さんは写真左)
——幸さんの夢の詰め合わせみたいな環境ですね!
その京都の保育園で4年かな、調理師として給食をつくって。
その園は子どもたちの部屋と給食室が近いから、園庭から子どもが窓を開けて給食室に喋りかけてくれたり、給食をいっしょに食べて「こういうのが食べたい!」っていう話を聞いたりもしました。
そんななかで子どもたちの苦手な野菜をおいしく食べられるように工夫したものや、アレルギー持ちの子どもでも食べられる料理を試行錯誤して調理したものが「おいしい!」って言ってもらえた時の嬉しさといったらね!

こども食堂の様子。子どもたちがおいしそうに食べる姿が印象的でした
——すごく充実した時間だったのが伝わってきます!そういう環境にいると、そのまま働き続けたいと思う気もしますが…
そう、だけど”子どもが好き”っていうのと”調理が好き”っていう気持ちが満たされて…次のステップに進んでも良いかなって思い始めたんです。
ちょうどそのタイミングでおじいちゃんが亡くなって、お寺とか”死”のことを考えるようになりました。それで葬儀屋さんに入りました。
——自分の道を進んで、やり切れた感覚があったのかもしれないですね。葬儀屋さんというのは、お寺に戻ることを決意してですか?
そうですね。「戻ってきて欲しい」って言われてはいたし、そろそろ戻らないとなっていうのは自分のなかであって。
ただ自分はお寺で生まれて、ずっとお寺側としていろんな人と関わってきたけど、葬儀や法要に実際に関わることはなかった。戻る前に、葬儀を受ける側というか、お檀家さん側の気持ちに触れてみたいと思ったんです。
葬儀ってその家にとっては人生に数回あるかないかのことだから、きっと分からないことだらけですよね。その感覚を少しでも知ることができたら、お寺の立場として応える時にもなにか変わるかなっていうのはありました。

「宗派やお寺によって作法が違ったりする。でもそういうのを押し付けずに、相手の想いを聞かないといけないなって思った」と葬儀屋での仕事で学んだことを振り返ります
こども食堂を、白川町の記憶を繋ぐ場所に
——その後、白川町に戻ってきたんですね。
私が白川に戻ることが決まった時に父が廣通寺を兼務する事になって、守り(もり)をするかたちで私が通う事になりました。初めての場所で不安もありましたけど、これがタイミングでご縁だったのかなぁって。
毎日通って本堂の窓を開けて空気を通わせるようになったら、お檀家さんから「お寺の空気が変わった。明るくなった。」って言われたんです。凄く嬉しかったですね。
廣通寺のお檀家さんも親切で優しい良い方ばかりで、すごくお世話になっています。そんななかで、何か少しでも地域の方々にお返しできないかなと思っていたんです。
——それが、お話のあった”こども食堂を始めるきっかけ”につながっていったと?
私の強みといえば調理だから、それで最初はお寺カフェなんかも考えていましたね。
やっぱり、お寺をいろんな人が気軽に利用できるようにしたかった。これだけの空間があって、それを利用しないのはもったいないというか。
結局、こども食堂は規模的にお寺じゃなくてふれあいセンター(公民館)でやることになったけど、親子だけじゃなくて広い世代に利用してもらいたいです。

廣通寺で子どもたちがスイカ割をする様子。多くの人が集まる、地域に開かれたお寺になっています
——広い世代、というのはきっと幸さんの「楽しかった」幼少期の経験からくるものですよね。
そうですね。お寺ってみんなが安心して集まれるところだと思うんです。
お檀家さんやいろんな人が遊んでくれて、家族ともいろんな思い出があります。隣のお兄ちゃんに自転車を教えてもらったこととか、そういう記憶は今でも鮮明に覚えていますね。
こども食堂でも、子どもたちにそういう思い出を残して欲しいんです。町内でつくった野菜に触れるとか、町の人と会うとか…だから、白川町が好きとか。
それが今じゃなくても「あの時はこれが楽しかった!」とか、そういう自分の生まれ育った地元の記憶がずっと残ってくれたら嬉しいですね。こども食堂が、それを繋げていける場所になって欲しいと思っています。
——そんな子どもたちを見ることで、他の世代の人も元気が出ますよね。
「これだけの子どもが白川町にはいるんだよ!」っていうのをみんなに見て欲しいし、世代関係なく近所の人と気軽に「いっしょにご飯食べに行こう」みたいな感覚で来て、いろんな人と触れあって欲しい!
そのためにも、まずは継続していきたいですね。

幸さんがこれまで積み上げてきた経験、出会いが、お寺を新しい場所に変えていく。
その過程は、自分の気持ちや境遇を大事にし続けた幸さんの生き方を示してくれているような気がしました。
【尾関 幸(おぜき さち)さん】
出身 :白川地区
学校 :関商工高等学校、京都調理師専門学校
職歴 :調理師
趣味 :食べたいものを自分でつくること
読んでくれている人に一言 :みなさん、気軽に足を運んでください!
取材年月:2025年9月
※記事の内容は取材当時のものです。