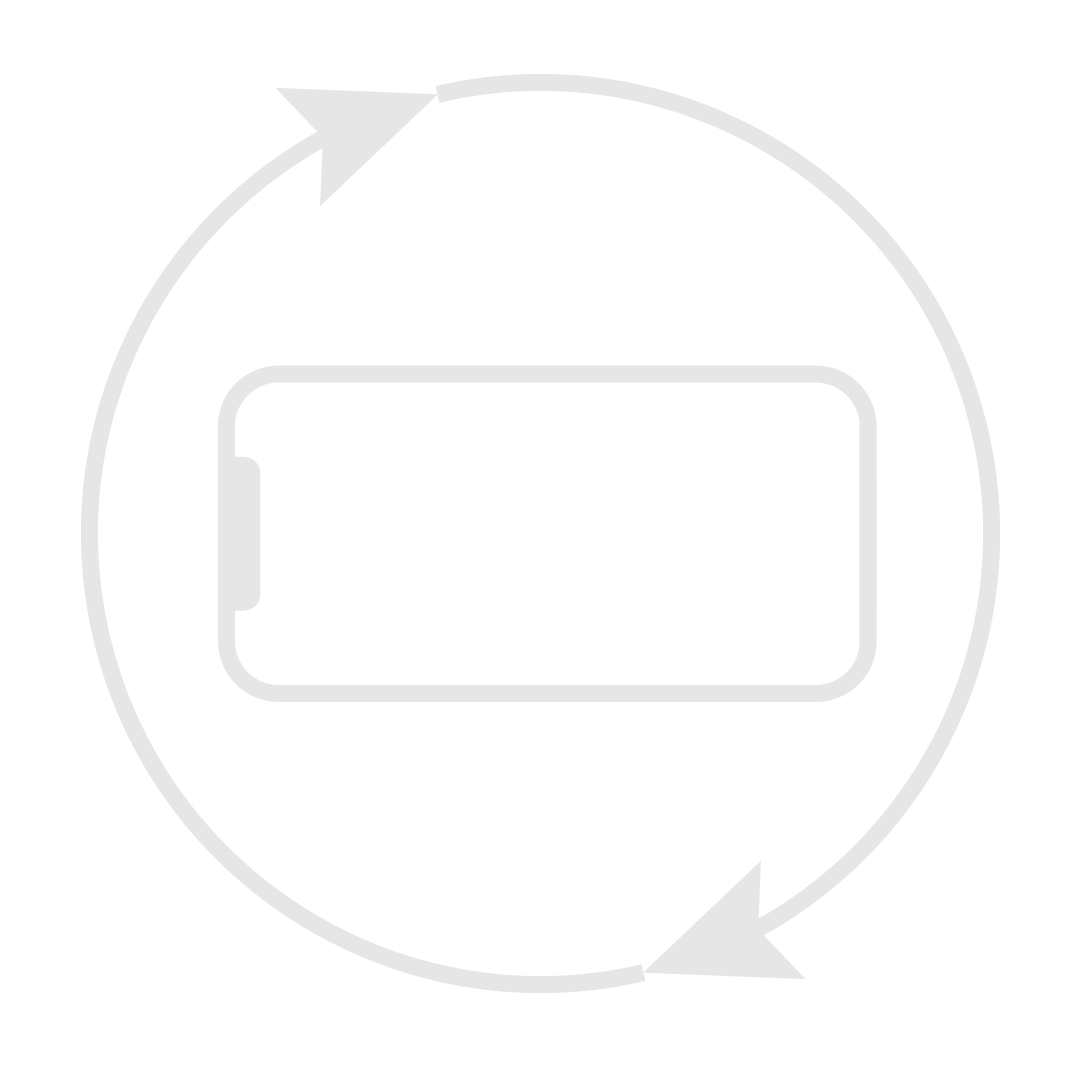白川北地区にある臨川寺(りんせんじ)*で、40年以上住職を務める加納明義(かのうみょうぎ)さん。
*1655年に開創された曹洞宗の寺院。本尊は『十一面観世音菩薩』、萬嶽堂には薬師如来座像、釈迦如来座像、阿弥陀如来座像や『十九体の仏群像』が保管され、白川町有形文化財に指定されています
生まれは長崎県の五島列島。これまで住職だけでなく、2023年度まで10年間にわたり白川町仏教会会長を務め、現在も白川町文化財保護審議会委員、保護司として活動しています。
社会が移り変わるなかで、変わらない仏の教えと向き合う加納さんにお話を伺ってきました。
五島列島の少年から、白川町のお寺の跡取りに
——白川町では、明治初期の苗木藩による廃仏毀釈*によって廃寺になったお寺もあります。ただ臨川寺は尾張藩の管轄だったこともあり、長い歴史がありますよね。
開創してから数えると、私は20世(現住8世)になります。
*明治初期に起こった仏教排斥運動。仏堂・仏像・仏具・経巻などに対して破壊行為が行われました

明治初期、飛騨川に漂着し臨川寺に保管された『十九体の仏群像』。廃仏毀釈により流されたものと考えられており、一木造の木彫りはおそくとも平安末期のものと言われています
——加納さんご自身が住職になられたのはいつ頃なんでしょう?
昭和57年(1982年)からなので、44年目ですね。
——44年…!すごいですね。
元々はね、生まれはここじゃないんですよ。長崎県の五島列島の出身なんです。
——五島列島…!
五島列島には久賀島(ひさかじま)っていう馬のひづめみたいな形をした島があるんですけど、そこに師匠が住職をしていた禅海寺というお寺があって、小学校1年生から6年生まで過ごしました。
禅海寺は師匠の長男が住職を継ぐ予定だったんですけどね…

目の前が海だったという五島列島の生活。白川町に引越した当初は「新鮮な魚が恋しかった」と振り返ります
——けど…?
師匠の長男が岐阜市のお寺の住職になったんですが、そこは境内地が広かったので、お庫裡さん(住職の奥さん)が保育園を始めたんです。昭和40年代の子どもがたくさんいる時代ですから、保育園をいくつも展開するようになって「保育園を辞めて五島に帰ってくるのは無理だ」と(笑)
——外で地盤を固めてしまったんですね(笑)
逆に師匠の長男から「老後の面倒も見れるしこっちにこないか?」という話があったみたいです。それで白川町の臨川寺が、住職が不在だったのがご縁で来ることになりました。
ちょうど小学6年生まで五島列島で生活して、こちらに来たのが中学校に上がる年だったんですよ。

飛騨川バス転落事故の慰霊のために建てられた『天心白菊の塔』。「五島にいる時にニュースで事故のことを知った」という加納さんは、高校生の頃から毎年法要に関わっています
小学生で受け入れた『住職への道』
–——数分のお話のあいだに五島列島の少年が白川町のお寺の跡取りに…
中学卒業後、愛知県豊川市の曹洞宗妙厳寺専門僧堂(豊川稲荷)で4年間修行しつつ、夜間定時制高校へ通っていました。そのあと大学へ進学して、卒業後臨川寺に戻ってきた形ですね。
——ではもう中学生の頃にお寺を継ぐことを決めたんですか?
たぶん、小学生の時点ですかね。小学1年生の頃からお経を読んで、法事とかお葬式にいっしょに行って、お盆の時期は一人で棚経(たなぎょう)も回ってましたから。
——小学生から…!加納さんにとって「住職になる」というのがしっくりくる選択だったんですね。
いや、もちろん葛藤はありましたよ。住職になるとか、お寺で生活するっていうことには。
ただ白川に来た時点で、師匠の長男はもう帰ってこないし、お檀家さんは跡継ぎもいっしょに来たと喜んでましたので(笑)
「諦め」じゃないけど、住職になるという道がもう敷かれている状態でしたね。
僧堂では修行僧が全員で100人近く、同じ安居者(同じ年に入った修行仲間)が28人いました。右も左もわからなくてすごく苦労しましたけど、お互いの助け合いで何とか乗り切れたと思います。それが私の高校生活ですね。

「お坊さんになるためには段階があるんです。先代の師匠は高齢だったので、資格も早く取っていかなきゃっていう気持ちがありましたね」
——ご自身の置かれた環境を受け入れるというか…そこから実際に住職になって40年以上ですもんね。
臨川寺はお檀家さんが多くないので、10年ぐらい病院で医療事務の仕事をしながら生活してたんです。それはしんどかったですね。病院では期限付きの仕事に追われて、当直や日勤があり、土日、盆、正月は檀務の仕事で忙しかったりで…体調を崩した時もありましたね。
忙しい年は1年間で3日4日しか休みがなくて、子どもたちと接する時間がほとんどなかったこともありました。
子どもたちがそんな親の姿を見て「おれもお坊さんになろうかな」っていう気持ちにはならないだろうなと思って…それで仕事を辞めることにしたんです。
だって生活は楽なほうがいいじゃないですか、誰しもがね(笑)

息子さんが頭を剃り、永平寺に修行に出た時の写真。「子どもたちの成長する姿を見るのが楽しみですよね」
仏教音楽で生まれる繋がり
——生活は大丈夫だったんですか?
仕事を辞めて3年ぐらいはかなり奮闘しましたね。まずはいろんな場所に顔を出して繋がりをつくるところからはじめて、他の寺院のお手伝をさせていただいて、なんとか少しずつ生活が成り立つようになりました。
あとはそれ以外にも、住職として“布教活動”をしながら生活のプラスアルファになれば良いなと思ったんです。
——布教活動、ですか。
曹洞宗では布教には大きく2種類あるんです。
1つは、法話を専門にお話をする『布教師』さん。お釈迦さまや、各祖師さま方の説かれた教えや生き方などをわかりやすく自分の言葉でお話しします。そのためには多くの書物を読んで、頭で理解、記憶しないといけないんですが、当時私は35歳ぐらいだったんですね。
普通は20代半ばぐらいから勉強に入る人が多く…これはちょっと大変だなと思って。
——たしかに住職の方と言えば、法話をしてくださるイメージがあります。
それでもう1つというのが『梅花流詠讃歌』(『ばいかりゅうえいさんか』:曹洞宗でお唱えする御詠歌・御和讃)なんですけど、これは仏教音楽なんです。

実際に使う道具を見せていただきました。「この譜面に書かれていること以外にも『アヤ』と呼ばれる、演歌でいう”こぶし”を入れるとか、そのほかいろいろと約束事があるんです」
——仏教音楽…?
生きる姿勢がメロディーに乗せて説かれてあって、これもお釈迦さま、各祖師さま、菩薩さまの基本的教えを説明して法要行事などでお唱えするんです。
「あ、これなら簡単にできるかも」と思ってね(笑)
——え、簡単なんですか!?
小さい頃、五島にいた時分から詠讃歌をやってるおばあさんたちがいて、夜本堂で練習してるのを聞いてたんです。だからメロディーが自然と身近にあったんですよ。それで簡単な気持ちで考えてましたが、実際は表面ではわからない約束事がたくさんあったりで、かなり奥が深いものでしたね(笑)

4月8日に行われる、お釈迦さまの誕生日を祝う『花祭り』の様子。この日も加納さんが編集した『梅花流詠讃歌』の曲が流れます
——加納さんにとって馴染み深い音楽だったんですね。
資格を取り、特派師範として地方を巡回させていただきました。
詠讃歌の指導で地方を巡回すると、知り合いの方、関係役職の方、詠讃歌を研鑽されておられる方々との交流ができるんです。
——同じものを学んでいる方々と。
詠讃歌を唱え、ご指導させていただくと、その一生懸命に取り組んでおられるみなさんの姿を見て心が引き締まる思いになるし、詠讃歌の魅力と楽しみがあって今も続けています。
”善”を優先して生活できる世の中へ
——「簡単にできるかも」から始まったものが、加納さんにとって大きな意味を持つようになったんですね…!加納さんは想定していたものと違ってもそれを受け入れて、道を切り開いているような印象を受けます。お寺の今後のこともお聞きしたいです。
人口も少なくなり新しい檀家さんはなかなか望めないと思いますね。
こういう言い方は失礼かもしれないけど…大家族から核家族へと変化して、若い人たちの宗教観が薄れてきていると思います。親の世代からお寺の付き合い方を教わったり、触れる機会が少なくなっている気がしますね。それにコロナの影響もあるのかな。
今は「老後子どもたちに迷惑をかけたくない」と思う親が多くなってきてるような気がします。本来は親なんだから「迷惑をかけたっていいんですよ」と私は思いますが…
——昔と比べて”繋がり”が薄れて、個人が優先されているというか。
『梅花流詠讃歌』は1952年に創立されたんですが「お唱えし、供養することで、心が和らげられる」っていうことで、当時はすごく人気だったんですよ!でも今の世の中は、いろんな楽しみ方がありますからね。梅花講(『梅花流詠讃歌』を学ぶ集まりのこと)に入講される人が減ってますし、高齢化が進んでいますね。
今じゃ簡単にカラオケに行ったり、家族でゲームを楽しんだり、携帯で楽しめることがたくさんあったりして…いろんな趣味の過ごし方があるんですよね。

詠讃歌の指導をされる加納さん。「詠讃歌を難しく感じる住職さんもいっしゃいますが、御詠歌があると法要が締りますよ。心地良いですね」
——人が減っているうえに、選択肢がたくさんある。でも逆に、情報量が多くて変化も早い時代だからこそ、何千年も変わらない教えがある宗教やお寺の存在って、すごく大事なんじゃないかと個人的に思うんですが…
今ね、お寺に人が集まって来るように、お寺を有効活用した催し物ができないかを考えてる段階なんですよ。
社会では自死の問題や「馬が合わない」「思うようにならない」「我慢の限界がきた」、そんな思いから人を傷つけるような事件がありますよね。みんな、”善悪“は分かってるんですよ。「言葉で人の命を奪う」とか「人を傷つけること」「人を騙すこと」が悪いことっていうのは当然分かってる。でも、衝動的にそれを抑えられない。
”善”を優先して生活できない世の中っていうのは、怖いですよね。それをどうやって伝えていけばいいのかが難しいです。今はSNSで多くの情報が流れてますが、一部の興味本位の捉え方で、部分的に拡散され間違って伝わる可能性も高い。何が真実なのか見極めて欲しいですね。やっぱりお寺に来て、話を聞いて、触れたり、感じたり、そういうことをするのが大事なのかなって思います。

「昔は元旦には本堂で互礼会をやってました。朝から夜の9時ぐらいまで。もうお話が尽きない、というか同じことのエンドレスなんですよ(笑)お酒が入るのでね。でもそれでいろんな話ができて、コミュニケーションも取れてましたね」
——歴史や先人の教え、想い、いろんなものが積み重なった場所や人だからこそ伝わるものがあるんですね。
今も保護司の活動をさせていただいているんですが、薬物担当の時に年に1 回、小・中・高校に「薬物乱用防止出前講座」(ダメ。ゼッタイ)に行く機会がありました。今は、ネット社会で簡単に薬物に手を出しやすくて、小・中学生にまで薬物の対象者が広がってるんです。
「出前講座」は年に1回だけで、しかも伝える時間は数十分です。短時間で子どもたちに薬物の恐ろしさが伝わってるのかどうかは分かりませんが「絶対に薬物に手を出さない、非行には走らない」ことを願っています。
お寺のこともそうですが、やっぱりひとつのことを続けていく、布教していくっていうのは難しいですよね。でもそれを踏まえながら、今後も社会活動を続けていけたらと思っています。

情報の多さや、攻撃的な言動、環境のこと。日常のなかには、不安になったり心が乱されることがたくさんあります。
仏教の道の上に在り続けた加納さんの生き方は、いつも自分が置かれた環境を受け入れたうえで、行動するものでした。それは今の社会との向き合い方のヒントになるような気がします。加納さん、ありがとうございました。
【加納 明義さん】
屋号 :屋号はありませんが、山号「萬嶽山」(ばんがくさん)
出身 :長崎県五島市
学校 :愛知学院大学(宗教学科)
職歴 :僧侶
趣味 :スポーツ、映画鑑賞 旅
読んでくれている人に一言 :これからますます厳しい時代へと向かっていきます。人口減少(児童減少含め)や、町内での働く場所も限られています。今は犯罪が横行した迷走な時代へと進みつつあるような気がします。一人一人が心にしっかりとした羅針盤を持ち、目標を誤らず進んで行って欲しいです。
又、梅花流詠讃歌にも興味を持って頂き、一緒にお唱え出来ればと思います。いつでも体験できますのでお気軽にお声をかけて頂けるとありがたいです。“あなたも仏の教えに触れてみませんか”
取材年月:2025年7月
※年齢、年数等の数字は取材当時のものです。