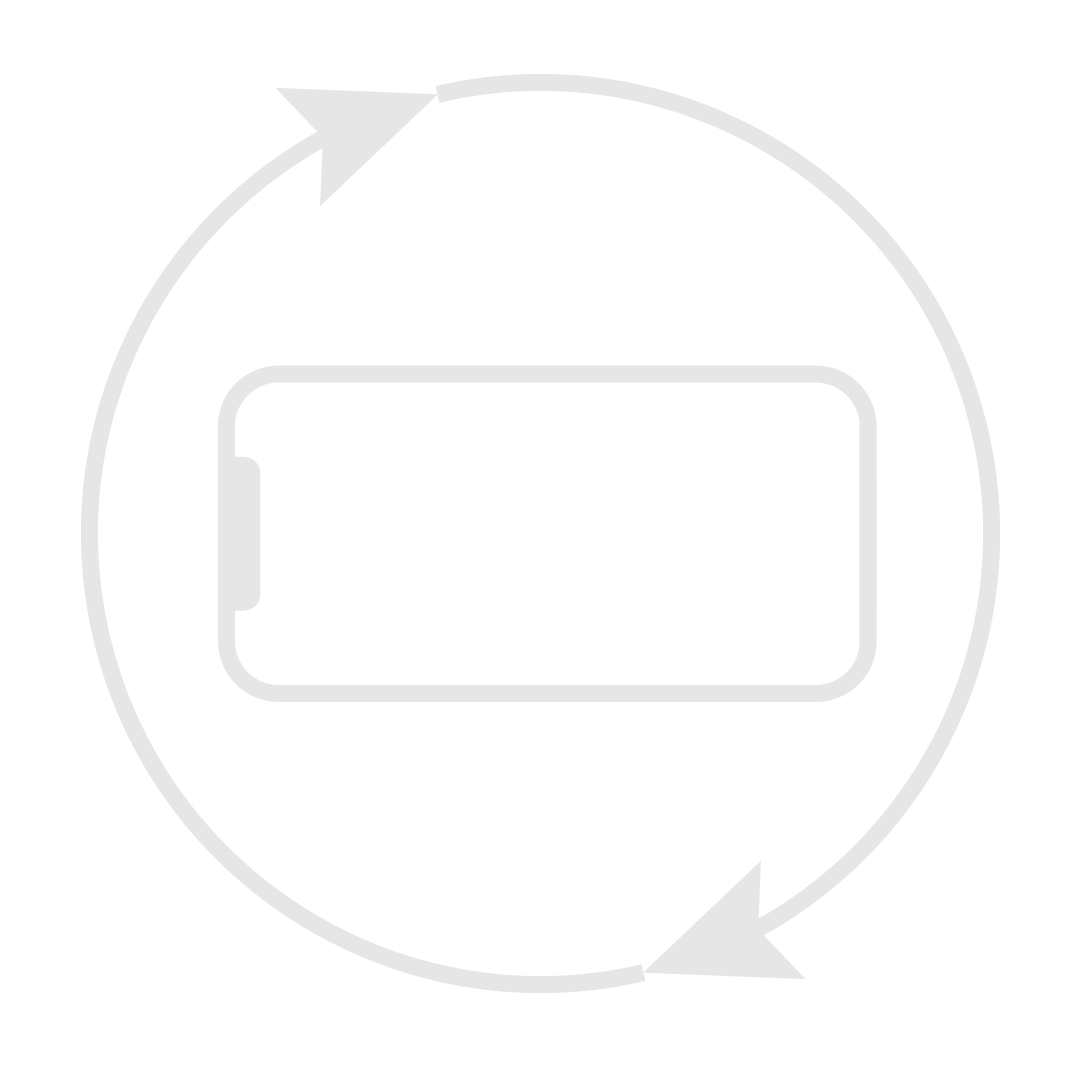蘇原地区切井にある佐長田(さながた)神社。春の例大祭では、五穀豊穣を願い1926年(昭和2年)から毎年『杵振り踊り』が奉納されます。
纐纈剛(こうけつたけし)さんは2017年、37歳の時Uターンで切井に戻り、現在は杵振り踊りを取り仕切る『賛助会』の代表を務めています。

2026年には100周年を迎える『杵振り踊り』。これまでは切井出身の中学生以上の男子が奉納していましたが、2024年には女性、切井出身者以外の参加も可能になりました
「2024年度で地域の保育園は閉園してしまうし、やっぱり人数が減るとこの町は無くなってしまう。それをいかに食い止めるか、そのためにもまずは白川町を知ってもらうことが大事だと思います」
仕事では観光業でお土産物の卸売りに関わり、その他にも保育園の閉園事業の代表を務めるなどさまざまな活動を行う剛さん。そのバイタリティ溢れる行動の先に目指すものを、お聞きしてきました。
町を残すために「声をあげられる人」になる
——剛さんは、切井でのあらゆる活動に参加されている印象があります。
めちゃくちゃ忙しいです(笑)ただ役などをお願いされたら基本は断らないようにしています。身体がもつ限りですけどね(笑)
僕がUターンで白川に帰ってきたのは37歳だったんですけど、年齢的なこともあってか引っ越してきても消防団の入団のお誘いはありませんでした。同級生のほとんどが当時消防団に入って、頑張って町を守ってくれていました。
なので僕はそれができなかった分、他の面でいろいろお手伝いしようっていうのがあって。

地域でたくさんの役を担う剛さん。「もともと僕はスポーツができないんで、小さい頃から知っている同級生は『あいつが消防団に入ってもなぁ』みたいなのがあったのかもしれないですね(笑)」
——そんな想いがあったんですね。
あとは、地区の高齢の方は知ってらっしゃいますがうちはもともと庄屋だったんです。その時代はいろいろと取り仕切っていたみたいです。
そういうのもあって、今は何もありませんが、切井なり白川町なりに僕がその時の恩返しができればいいなって想いがあります。
–—–そういったことがUターンを決意するきっかけになったんでしょうか。
決意したというより、子どもの頃から友だちと「いつかは帰る」みたいな話はよくしていて、そういうものだと思ってましたね(笑)もともと都会よりも、人間関係がしっかりある下町とかのほうが好きなんです。
なので、帰ってきたきっかけっていうのは特になくて「そろそろ家建てたりしないとまずいかなぁ…」とか、そういうので37歳になった感じです(笑)
——剛さんにとって、白川町が”いつか帰りたい居心地の良い場所”だったんですね。
高校卒業後から勤める会社はいくつか転々としましたけど、基本的には実家に帰っても通える範囲で探していました。
22歳の頃から一緒にいる妻には、切井に住む前提でずっと話をしていましたね。今では僕より切井に馴染んでいます(笑)でもそれはすごく嬉しかったです。

「昔同級生と『お前は帰ってくるよな?』って話してた記憶があります。けっきょく彼はまだ美濃加茂のほうに住んでますけどね(笑)でも本人の自由でええやんと今では思ってます」
——実際Uターンされて感じるものってありましたか?
なんだろうなぁ…やっぱり、杵振り踊りをまた踊れるようになったのは嬉しかったですね。
実は僕、白川町に住んでる期間ってけっこう短いんですよ。保育園の年長の時に愛知県から親父の実家である切井に帰ってきて、中学卒業と同時に下宿に住むため外に出てるんです。
——もう高校生から町外に!Uターンで戻られるまでに20年以上あったんですね。
杵振り踊りは中学生以上の男子が踊るので(2024年から中学生以上の男女、町外在住者の参加も可能に)、中学校の3年間しか踊ってない。それでUターンで帰ってきて久々に春祭りを見た時に「良いなぁ、懐かしいな」って思ったんです。やっぱり子どもの頃の切井での生活でいちばん覚えているのは夏祭りと春祭りで、春祭りの時は杵振り踊りを「カッコいいなぁ」って思いながら見ていたので。
それで翌年、中学生の時ぶりに杵振り踊りに参加させてもらったらめちゃくちゃ楽しかったんですよね。「うわ、楽しい!」って、それでこれは毎年やっていこうって決めました。

夏のお祭りでも出店に関わる剛さん。「元々は関わってなかったけど、同級生に『今年いけないから代わってくれ』って言われてやったら、なぜかそこからずーっと僕の役になっています(笑)」
——地域での伝統は子どもの頃からの憧れでもあった、と。杵振り踊りは2024年から女性や町外在住者の希望者も参加するようになりました。それは参加人数の増加や踊りの継続には大きな変化だと思いますが、同時に地元の人の関わりが減り”伝統的な側面”が失われる、ということはありませんか?
どうでしょうね…ただやっぱり続けていくには地元の人にも参加してもらいたい。そのためにも魅力的なものにしないと「やりたい!」と思わないじゃないですか。
見ていてカッコいいとか、憧れになるような存在になっていければ、おのずからどんどん人が増えていくんじゃないかなと思います。そうすれば切井に残ってくれる子や、また帰ってきてくれる子が増えるかもしれない。そのようなサイクルができると嬉しいですね。
——小さい頃の楽しかった記憶ってずっと無くならないですもんね。地域の伝統が、憧れや愛着として残り続けるかもしれない。
僕より上の世代は中高生の男子だけでも人が多くて、踊りたくても踊れない子もいたらしいんですよ。だから踊ること自体が由緒あることだったみたいで。
僕たちの世代では暗黙の了解で半強制でした。踊ることができたので結果良かったですけどね(笑)…でも今はそのような時代ではないかな、と。伝統も残しながら、時代の流れに沿って変わっていけばいいんだと思うんです。
祭り当日になったら集合場所に「うぃーっす」とか言って、町外に住んでる人や久しぶりの人がどんどん集まって来る(笑)祭りのために帰省してくれる子もいて、普段は若い子の姿をあまり見ませんが、あの時は運営側に立つと嬉しいですね。

2025年4月の佐長田神社春の例大祭の様子。当日は雨でしたが、多くの人で賑わいました
——祭りの当日はすごい人ですよね!ただ2024年度で地域の保育園が閉園してしまうなど、人数が減っている実情もあります。
僕は保育園の閉園事業の代表もやってますけど、やっぱり自分が卒園した保育園の閉園の旗を降るのなんて嫌ですよ(笑)未だに僕は閉園することに反対だけど、引き受けた以上は最善を尽くして園児や保護者の意向を叶えるようにしています。
このような事が続くと人数が減っていってしまって、この町は無くなってしまうと思うんです。それを食い止めて地域サービスを低下させないようにやっていけるのが理想ですよね。じゃないとせっかく移住して来てくれる人もいるのに、不便になっていくのは申し訳なくて…
そのためにも僕は声を上げていける人になりたいです。そうするとたぶんすごい嫌がられることもありますけどね(笑)なので感情的にではなく建設的な意見をするように心がけています。

剛さんが事業の代表を務めた蘇原保育園閉園式では、園舎を一望できる気球が飛びました
地域活動のきっかけは『モネの池』
–——結果的に町のためになる行動、というのはありますが、剛さんはそもそも「町のために」行動している印象があります。そういった意識はいつ頃から生まれてきたんでしょうか?
3つ程ありますが、言うのであれば観光業で土産物に携わる仕事で営業をしていて、自分が動くことで結果が変わることを経験したのが大きいと思います。
岐阜県の関市に『モネの池』*って言われる場所があって、2016年ぐらいからSNSで有名になったんです。
*『名もなき池』:関市板取の根道神社境内にある、フランスの画家クロード・モネの名画「睡蓮」にそっくりと話題の、通称「モネの池」。透明度の高い湧水に咲く睡蓮がとても美しく、池の中を優雅に錦鯉が泳ぐ姿は連日、多くの人で賑わっています。農業用ため池で観光用の池でもない無名の池が、SNSで話題になったことで一躍有名になりました。(https://sekikanko.jp/spot_post/162より参照)
——剛さんがUターンされる少し前ですよね。
そうです。とある道の駅で仕事をしていたらお客さんに「『モネの池』ってどこですか?」って聞かれたんですよ。僕はまったく知らなかったんだけど、調べたらすごく綺麗な写真で、後日行ってみたんです。
そしたら切井と変わらない田舎にお客さんがたくさん来ていて…「これは乗っからない手はない!」と思いました。

2016年に剛さんが撮影した『モネの池』
——「人気が出るだろうから『モネの池』に関わるお土産物をつくろう!」、と。
そうです、その時はただただ商売の話でね(笑)でも名前を使うなら許可を取らないといけないから、神社庁とかいろいろ連絡をしたり現地の白谷地区自治会長さんとも繋がって、自治会の人ともすごく仲良くなりました。
話を進めていく過程で「たくさんの人が見に来てくれるのは嬉しいけど、清掃や維持費などに困っている」という話が出て、売り上げの何%かを自治会に寄付する形で商品を販売することになったんです。
——それは、売れたらみんなハッピーな形ですよね。
で、実際めちゃくちゃ売れたんですよ(笑)僕の営業人生で一番うまくいった案件です。
数年後、自治会長さんが「見物客が多すぎて池の周りが崩れちゃうから、今度整備して車いすも通れるようにする。君らから貰ったお金でつくるから、今度その祈願祭に来てよ」って言ってくれて。
実際に参加して、新聞社に声をかけ後日新聞にその記事がうまいこと掲載されさらに注目されました。

寄付金を使ってつくられた歩道
——すごい、ほんとにみんなハッピーな形になっていますね…!
そういうふうに、僕らのやった仕事がお金を生んで、上手に使われるような仕組みを地元の人たちといっしょにつくれたことがすごく嬉しくて。地域も、僕らも、観光に来る人も、三方良しですよね。今でも半年に1回はそこに行ってみんなといろいろお話して、神社にお参りするんです。感謝の意味を込めてお賽銭は紙幣を入れてます(笑)
それは地域活動を頑張れるようになったきっかけのひとつでもあるかなと思います。
——どうしても町のための活動ってボランティア的なものになってしまいがちですよね。もしビジネス的な側面でうまくいけば、持続的に町が発展していける。
想いがあってもビジネスとして成り立たせることはなかなか難しいです…!でもそれがうまくいったことで、すごくやっていて楽しかったのと達成感があって「外でできるなら自分の地元でもやらないと」、と。
白川町で何かできないかって、ほんとにいっつも考えてますよ。あとはそれが実現するかどうかですけど、本気でいつも考えてます。

剛さんと、当時の白谷地区自治会長さん
膝にきても、踊りは生涯現役!
——そういう想いを行動に移すことで「町がこうなって欲しい」という理想はありますか?
白川町、切井を残していくっていうことに対して、もっとみんながフットワーク軽く動けるようになれば良いなと思います。諦めモードとかじゃなくて「ちょっとひと暴れしてやろうか」みたいなね(笑)
——移住者の増加や新しい事業、イベントなど、盛り上がることはたくさんあると思います。でもどうしても少子高齢化は進むし、ネガティブな意見はなくならないですよね。
これを言うと怒られるかもしれませんが、切井っていう地域は周りからよく「保守的だ」って言われるんですよ。新しいことにアレルギーがあるっていうか。
そこで自分が実際に行動していくことで、少しでも新しいことにチャレンジできる土壌になっていくと良いかなと思っています。バイタリティ、アクションとかを、どんどん生み出していきたいですよね。
でももちろん昔からは変わってきていて、僕がUターンで戻って来た時には「昔はもっと閉鎖的な地域だったよなぁ」って思いました。それはたぶん、僕がいない間に住んでいた方や移住で来られた方たちが良い方向に変えてきたんだろうなと。

地元の小学6年生に杵振り踊りのことを伝える剛さん。地域を盛り上げるため、新しい取り組みをどんどん始めています。「切井に移住してくれるのは非常にありがたいんで、来てくれれば僕がサポートします!(笑)」
——これまでの人たちの積み重ねで今がある、と。
2026年は杵振り踊りが100周年なんです。人数とかも含めていろいろと課題はあるので、今考えていることを実現できるようにしていきたいです。僕はできれば生涯現役、やれる限りは踊ろうと思ってるんで!この年齢で踊ると、けっこう膝にきますけどね(笑)
そうやって、まずは白川町を知ってもらいたい。来てくれる人たちに、切井だけじゃなくて白川町が良いところだって思ってもらえて、興味を持ってもらえれば嬉しいですよね。

「帰ってきてもそんなにギャップはなかったですね。外にいる時からちょこちょこ帰省してたし、畑をやったりするのもすごい好きなんです」
地域で先頭に立ち行動を続ける剛さん。それは剛さんの幼少期に町への愛着を培ったあらゆるものを、心を動かしたあらゆる体験を、次の世代に受け継いでいるかのようでした。
【纐纈 剛さん】
屋号 :栗本
出身 :蘇原地区
学校 :蘇原小学校→白川中学校→東濃実業高校
職歴 :半導体製造業と副業で飲食業→観光土産業営業
趣味 :いっぱいありますが、お酒を楽しく飲むことが1番です。
読んでくれている人に一言 :一言ではなくすみません。白川は何もないでな・・・、なんて言わせないように一緒に頑張ってくれる人、お声かけ下さい。
賛助会も何時でも参加募集しております。杵振り踊りを続けるためのサポートを一緒にしませんか?
取材年月:2025年2月